この記事では絵の具や色鉛筆、
クレヨンなどで「茶色」を作りたい
初心者から中級者の方に向けて
書かれています。
茶色は一見シンプルな色に見えますが、
実際に自分で作ろうとすると
意外と難しく思い通りの色合いに
ならないことも多かったりします。
そこで本記事では、
基本の三原色を使った茶色の作り方から
画材ごとの混色テクニック、
失敗しないためのコツや
応用色の作り方まで、
プロの視点で徹底解説します!
色の理論や調整ポイントも
詳しく紹介するので、
誰でも理想の茶色を自在に
作れるようになります。
「茶色の作り方」で悩んでいる方は、
ぜひ最後までご覧ください。
目次
茶色の作り方を徹底解説|なぜ茶色は難しいのか?

茶色は、赤・青・黄などの
原色を混ぜて作ることができる
中間色の一つです。
ですが、混ぜる色の比率や順番、
使う画材によって仕上がりが
大きく変わるため、
思い通りの茶色を作るのは
意外と難しいと感じる人が多いです。
また、茶色には
- こげ茶
- 薄い茶色
- 赤みのある茶色
といったバリエーションが豊富で、
用途やイメージに合わせて
微調整が必要です。
この章ではなぜ茶色作りが難しいのか、
その理由や背景を詳しく解説します。
茶色はどんな色?印象・活用シーンを理解しよう
茶色は、自然や木、土、動物などを
連想させる温かみのある色です。
落ち着きや安心感、ナチュラルな
雰囲気を演出できるため、
イラストやデザイン、インテリアなど
幅広いシーンで活用されています。
また、茶色は他の色と組み合わせやすく、
背景色や影色としても重宝されます。
茶色の印象や使いどころを知ることで、
より効果的に色作りや配色が
できるようになります。
- 木や土、動物など自然を表現するのに最適
- 落ち着きや温かみを演出できる
- 背景や影色としても使いやすい
なぜ『茶色の作り方』が知りたい人が多いのか
茶色は絵の具セットや色鉛筆セットに
入っていることも多いですが、
微妙な色合いの調整や、
手持ちの色だけで作りたい場合には
自分で混色する必要があります。
また、こげ茶や薄い茶色など、
既製品では表現しきれない
色味を出したいときにも
「茶色の作り方」
を知っておくと便利です。
さらに、
「黒を使わずに深みのある茶色を作りたい」
「画材ごとに最適な混色方法を知りたい」
というニーズも多く、
茶色作りのコツや理論を知りたい人が
増えています。
実際に僕自身、茶色を使う際は
茶色一色ではなくて、
数種類の茶色を使って
制作をする場面がほとんどです。
それはキャンバスサイズの大きさに関わらず、
絵作りにおいて微妙な違いではあるものの、
その変化が仕上がりに少なからずの
影響を及ぼす事になる為でもあります。
- 手持ちの色だけで茶色を作りたい
- 微妙な色合いを自分で調整したい
- 黒を使わずに深みのある茶色を作りたい
- 画材ごとの混色方法を知りたい
三原色を使った基本の茶色の作り方と混色の理論

茶色を作る基本は、赤・青・黄の
三原色を使った混色です。
三原色の配合バランスや
混ぜる順番によって、
明るさや深み、赤みや黄みの強さが
変わります。
また、混色の理論を理解することで、
失敗しにくく、狙った色合いに
近づけることができます。
この章では、三原色の基本や
茶色作りの理論、
配合例、バリエーションの
違いについて詳しく解説します。
絵の具の三原色とは?色の作り方の基本原則
絵の具における「三原色」とは、
- 赤(マゼンタ)
- 青(シアン)
- 黄(イエロー)
これら3色を指します。
この三原色は、どの色とも混ぜることで
さまざまな色を作り出すことができる
基本の色ですので、
知らなかった方は
是非とも覚えておいてください。
これら三原色を混ぜる際は、
色の性質や混ぜる量によって
発色が大きく変わるため、
少しずつ加えて調整するのがポイントです。
また、三原色の組み合わせによって、
オレンジや緑、紫などの
中間色も作ることができ、
茶色もこの理論を応用して作ります。
色作りの基本原則を理解しておくことで、
失敗を防ぎやすくなります。
- 赤・青・黄が三原色
- 三原色の組み合わせで多彩な色が作れる
- 少しずつ混ぜて調整するのがコツ
三原色(赤・青・黄)で作る茶色の方法と配合例
茶色を作る基本的な方法は、
赤と黄色を混ぜてオレンジ色を作り、
そこに青を少しずつ加えていくやり方が
初心者の方でもやり易い方法です。
この際に、青を入れすぎると
黒っぽくなりすぎるため、
少量ずつ加えるのがポイントです。
また、赤・青・黄を同じ比率で混ぜると、
ややくすんだ茶色になります。
ですので、配合例としては
赤2:黄2:青1
この割合が標準的な茶色に近い
色味となります。
この配合に関しては自分のイメージに合わせて
赤みや黄みを調整してみましょう。
- 赤2:黄2:青1 標準的な茶色
- 赤2:黄3:青1 黄みの強い明るい茶色
- 赤3:黄2:青1 赤みの強い茶色
比率・割合で変わる茶色のバリエーション一覧
茶色は三原色の配合比率を変えることで、
さまざまなバリエーションを
作ることができます。
例えば、黄色を多めにすると
明るく温かみのある茶色に、
赤を多めにすると赤みの強い茶色に、
青を多めにすると深みのある
こげ茶色になります。
また、白を加えることで
薄い茶色やベージュ系の色も作れます。
下記の表を参考に、
あなた好みの茶色を作ってみましょう。
- 赤2:黄3:青1 明るく黄みの強い茶色
- 赤3:黄2:青1 赤みの強い茶色
- 赤2:黄2:青2 深みのあるこげ茶色
- 赤1:黄1:青1+白 薄い茶色・ベージュ
理想の色合いに仕上げる調整のポイント
理想の茶色に仕上げるためには、
混ぜる順番や量の調整が重要です。
まずは赤と黄色でオレンジを作り、
そこに青を少しずつ加えていきましょう。
色が濃すぎる場合は白を加えて明るくし、
薄すぎる場合は赤や青を足して
深みを出していきます。
また、混ぜすぎると
色が濁ることがあるので、
その都度様子を見ながら
少しずつ加えるのがコツです。
自分のイメージに近づくまで、
少量ずつ調整を繰り返しましょう。
- オレンジを作ってから青を加える
- 白で明るさを調整
- 混ぜすぎに注意!
- 少量ずつ加えて微調整
色鉛筆・クレヨン・水彩での茶色の作り方

茶色の作り方は、使う画材によっても
コツや手順が異なります。
色鉛筆やクレヨン、水彩絵の具など、
それぞれの特性を活かした
混色方法を知ることで、
より美しい茶色を表現できます。
この章では、画材ごとの茶色の作り方や、
薄い茶色からこげ茶色までの調整方法を
詳しく解説します。
色鉛筆でできる茶色の作り方とコツ
色鉛筆で茶色を作る場合、
重ね塗りがポイントとなります。
まず黄色やオレンジ系の色をベースに塗り、
その上から赤や青を重ねていくことで、
深みのある茶色を表現できます。
色鉛筆は透明感があるため、
力加減や重ねる順番によって
色味が大きく変わるという事を
意識しておくと良いでしょう。
また、こげ茶色を作りたい場合は、
青や紫を少し加える事で深みが増します。
紙の質感や塗り方によっても
発色が異なるので、
試し塗りをしながら
調整しましょう。
- 黄色やオレンジをベースに塗る
- 赤や青を重ねて深みを出す
- 力加減で色の濃さを調整
- こげ茶色は青や紫をプラス
水彩・クレヨンなど画材別の混色テクニック
水彩絵の具では、パレットの上で
色を混ぜてから塗るのが基本で、
そこに青を少しずつ加えて茶色にします。
絵の具は水の量を調整することで、
薄い茶色や濃い茶色も自在に作れます。
混色をし過ぎてしまうと
色が濁ってしまう恐れがあるので、
色数は絞って混色をしていきます。
クレヨンの場合は、
紙の上で色を重ねて混色します。
黄色やオレンジを塗った上に
赤や青を重ね、
指やティッシュでなじませると
自然な茶色になります。
画材ごとの特性を活かして、
理想の茶色を目指しましょう。
- 水彩はパレットで混色、水で濃淡調整
- クレヨンは紙の上で重ね塗り
- 指やティッシュでなじませると自然な色合いに
薄い茶色からこげ茶色まで色味の調整方法
薄い茶色を作りたい場合は白を加えたり、
水彩なら水を多めに使うことで
明るくなります。
逆に、こげ茶色を作りたい場合は、
青や黒、紫を少量加える事で
深みが増していきます。
また色鉛筆やクレヨンでは、
重ねる色の順番や力加減で
濃淡を調整できます。
どの画材でも、少しずつ色を加えて
様子を見ながら調整するのが
失敗しないコツです。
自分のイメージに合わせて
何度も試し塗りをしてみましょう。
- 薄い茶色は白や水を加える
- こげ茶色は青・黒・紫を少量プラス
- 重ね塗りや力加減で濃淡調整
黒なしで作る!失敗しない茶色の作り方のコツ

茶色を作る際に黒を使う事で、
色が濁りやすく思い通りの発色に
ならない事があります。
そこで黒を使わずに三原色や
補色を活用することで、
透明感や深みのある茶色を
作ることができます。
この章では、黒を使わない理由や、
彩度・明度のコントロール法、
補色や白・オレンジを使った調整術を
解説します。
黒色を使わない理由と彩度・明度のコントロール法
黒色を加えると茶色がくすんだり、
重たくなり過ぎることがあります。
そのため、三原色や補色を使って
彩度や明度を調整するのが
プロのテクニックです。
明るさを出したい場合は白や黄色、
深みを出したい場合は
青や紫を少量加えていきます。
彩度を下げたい時は、
補色同士を混ぜる事で
自然な落ち着きが生まれます。
綺麗な茶色を作る際は
黒を使わずに色をコントロールする事で、
透明感のある美しい茶色が作れます。
- 黒は色を濁らせやすい
- 三原色や補色で調整する
- 白や黄色で明るさを出す
- 青や紫で深みをプラス
黒を使わずに深みや立体感を出す補色の組み合わせ
補色とは、色相環で正反対に
位置する色のことです。
例えば、オレンジと青、赤と緑などが
補色の関係にあります。
茶色を作る際、オレンジに青を加えると
深みのある色合いになり、
黒を使わなくても立体感や
奥行きが出せるようになります。
補色をうまく使うことで、色が濁らず、
鮮やかさを保ったまま深みを
出すことができます。
色のバランスを見ながら、
少しずつ補色を加えて調整しましょう。
- オレンジ+青で深みのある茶色
- 赤+緑で落ち着いた茶色
- 補色を少しずつ加えて調整
白色やオレンジで理想の茶色を作る調整術
白色を加えると茶色が明るくなり、
ベージュやカフェオレといったような
色合いになります。
オレンジを加える事で、
温かみや鮮やかさが増し、
赤みのある茶色に仕上がります。
自分のイメージに合わせて、
白やオレンジを少しずつ
加えて調整することで、
理想の茶色を作ることができます。
特に明るい茶色や柔らかい
印象を出したい時は、
白やオレンジの活用が効果的です。
- 白で明るく柔らかい茶色に
- オレンジで温かみや赤みをプラス
- 少しずつ加えて好みの色に調整
こげ茶色・薄い茶色ほか応用色の作り方一覧

茶色には、こげ茶色や薄い茶色、
明るい茶色など、
さまざまなバリエーションがあります。
これらの応用色は
基本の茶色に特定の色を加えたり、
配合比率を変えることで
簡単に作ることができます。
また、レジンや手芸などのクラフトでも
茶色の調合方法を知っておくと、
作品の幅が広がります。
この章では、こげ茶色や薄い茶色の作り方、
手芸や他の原色を活かしたアレンジ法まで、
応用的な茶色の作り方を詳しく紹介します。
こげ茶色の作り方と配色バリエーション
こげ茶色は、基本の茶色に青や黒、紫を
少量加えることで作ることができます。
青や紫を加えると深みが増し、
黒を加えるとより重厚感のある
こげ茶色になります。
ただし、黒を入れすぎると色が濁る為、
少しずつ加えながら調整していくと良いです。
また、赤みや黄みを強調したい場合は、
赤や黄色を追加して自分好みの
こげ茶色に仕上げることも可能です。
- 茶色+青 深みのあるこげ茶色
- 茶色+黒 重厚感のあるこげ茶色
- 茶色+紫 赤みのあるこげ茶色
薄い茶色や明るい茶色の作り方
薄い茶色や明るい茶色を作るには、
基本の茶色に白や黄色を加えるのが
効果的です。
白を加えるとベージュや
カフェオレのような
柔らかい色合いになり、
黄色を加えると明るく温かみのある
茶色になります。
水彩の場合は、水を多めにして
薄める方法もおすすめです。
少しずつ色を加えて、
好みの明るさや薄さに調整しましょう。
- 白を加えてベージュ系に
- 黄色を加えて明るい茶色に
- 水彩は水で薄めて調整
レジンや手芸でも使える茶色の調合方法
レジンや手芸で茶色を作る場合も、
基本の色の混ぜ方は同じです。
レジン用の着色剤や
アクリル絵の具を使い、
赤・黄・青を混ぜて茶色を作ります。
こげ茶色や薄い茶色も、
配合比率や白・黒の加え方で
調整可能です。
透明感を出したい場合は、
着色剤を少なめにしてレジン液を
多めに使うと良いでしょう。
手芸用の粘土や布用絵の具でも
同様の方法で茶色を作る事が
できます。
- レジン着色剤やアクリル絵の具で混色
- 配合比率で色味を調整
- 透明感は着色剤を少なめに
他の原色・色味を活かした茶色のアレンジ法
茶色は、他の原色や補色を活かして
さまざまなアレンジが可能です。
例えば緑を加えると
落ち着いたアースカラーになり、
オレンジを加えると
温かみのある茶色に
変化します。
また、紫や青を加えることで、
より深みや個性的な茶色を作ることも
できます。
自分だけのオリジナル茶色を
作りたい時は、
いろいろな色を試して
みるのがおすすめです。
- 緑を加えてアースカラーに
- オレンジで温かみをプラス
- 紫や青で深みを出す
茶色作りを失敗しない為のQ&Aとプロのアドバイス

茶色作りでよくある失敗や
疑問を解決するために、
Q&A形式でプロのアドバイスを
まとめました。
彩度や明度の調整、色の作り方に
迷ったときの早見表の活用法など、
実践的なコツも紹介します。
これを読めば、茶色作りで困った時でも
安心です。
よくある失敗パターンとその解決策
茶色作りでよくある失敗には、
色が濁ってしまう
思ったより暗くなりすぎる
赤みや黄みが強すぎる
などがあります。
色が濁る場合は、
黒や青を入れすぎていないか確認し、
少しずつ色を加えることが大切です。
暗くなりすぎた場合は、
白や黄色を加えて明るさを調整しましょう。
赤みや黄みが強すぎる場合は、
青や補色を少量加えてバランスを整えると
自然な茶色になります。
失敗したときは、慌てずに
少しずつ色を調整するのがポイントです。
- 黒や青の入れすぎに注意
- 明るさは白や黄色で調整
- 赤み・黄みは補色でバランス調整
彩度・明度・深みをうまく調整するプロのコツ
彩度を下げたいときは、
補色を少しずつ加えることで
自然な落ち着きが生まれます。
明度を上げたい場合は白や黄色を使い、
深みを出したい場合は
青や紫を加えるのが効果的です。
また、混色は一度に多くの色を加えず、
少しずつ様子を見ながら
調整するのがプロの基本です。
色が濁らないように、
混ぜる順番や量に注意し、
都度試し塗りをして確認しましょう。
自分のイメージに近づくまで、
根気よく微調整を繰り返すことが大切です。
- 補色で彩度を調整
- 白・黄色で明度アップ
- 青・紫で深みをプラス
- 少しずつ混ぜて微調整
色の作り方に迷ったときの一覧・早見表活用法
色の作り方に迷った時は、
配合比率や混色例をまとめた
早見表を活用すると便利です。
早見表には、三原色の配合パターンや、
こげ茶色・薄い茶色などの
応用色の作り方が
一覧で載っています。
自分のイメージに近い色を見つけたら、
その配合を参考にして
混色を始めましょう。
また、色見本を作っておくと、
次回以降もスムーズに
理想の茶色を再現できます。
早見表や色見本を活用して、
効率よく色作りを楽しみましょう。
- 配合比率や混色例を一覧で確認
- 色見本を作っておくと便利
- 早見表で迷わず色作り
まとめ|自分だけの茶色を自在に作るために
茶色は三原色のバランスや混ぜ方、
画材ごとの特性を理解することで
誰でも自在に作ることができます。
基本の理論を押さえつつ、
少しずつ色を加えて微調整するのが
失敗しないコツです。
こげ茶色や薄い茶色など、
応用色も配合や補色の工夫で
簡単に作れます。
早見表や色見本を活用しながら、
自分だけの理想の茶色を
見つけてみてくださいね!
色作りの楽しさをぜひ体験して、
作品の幅を広げていきましょう。
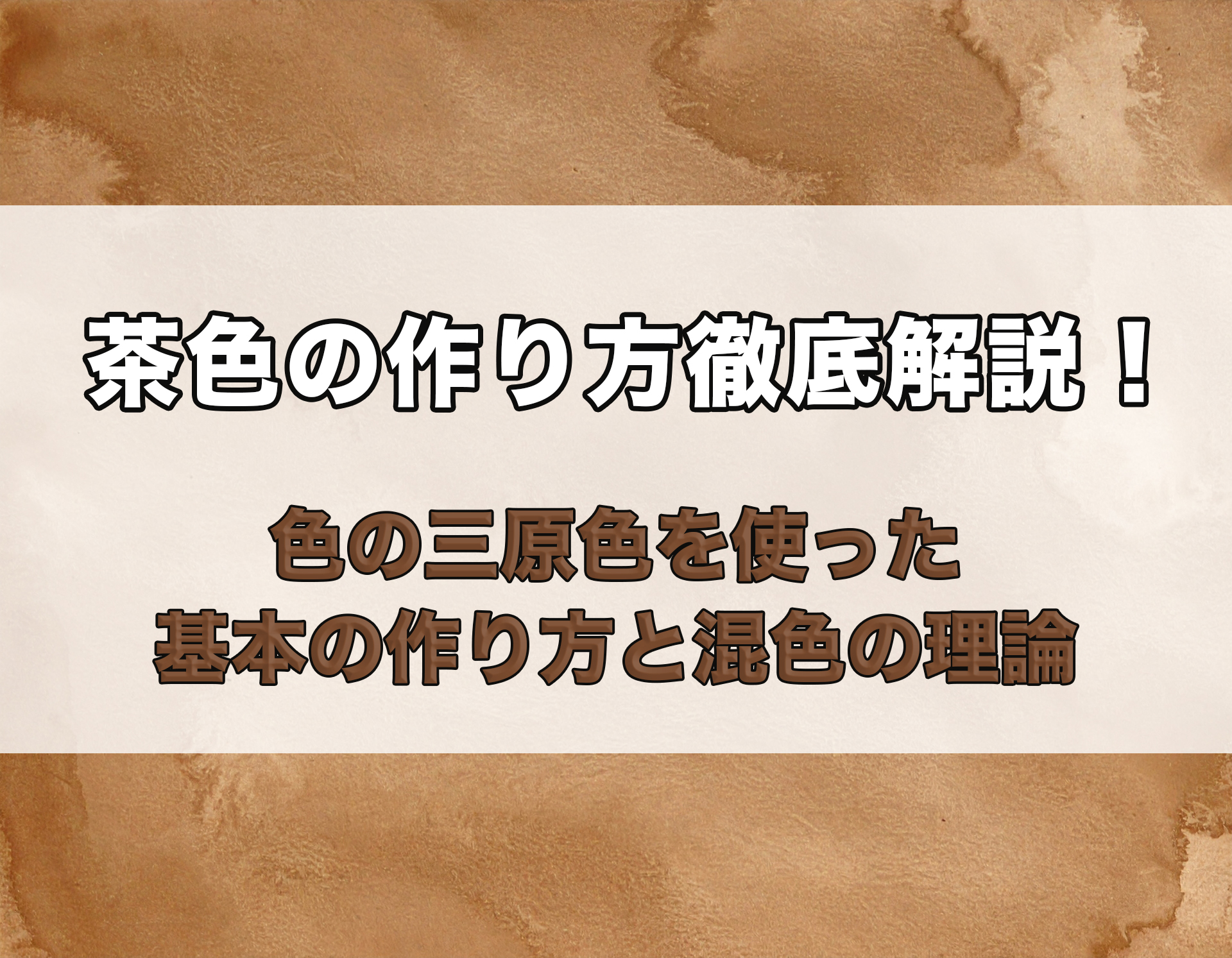
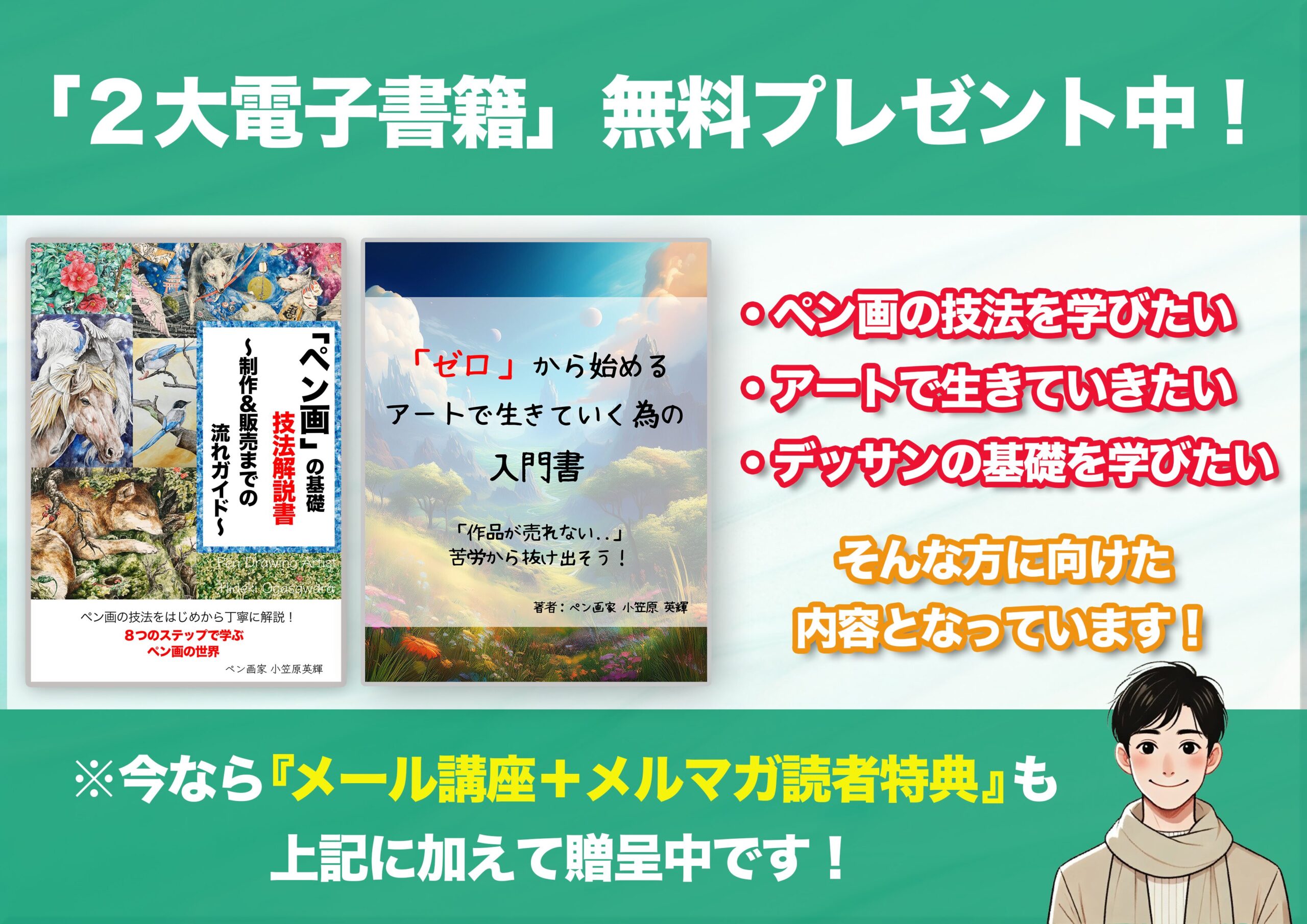



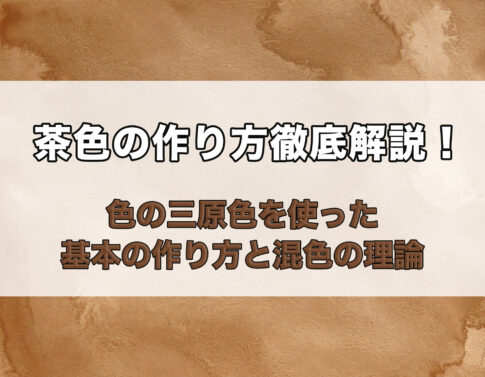


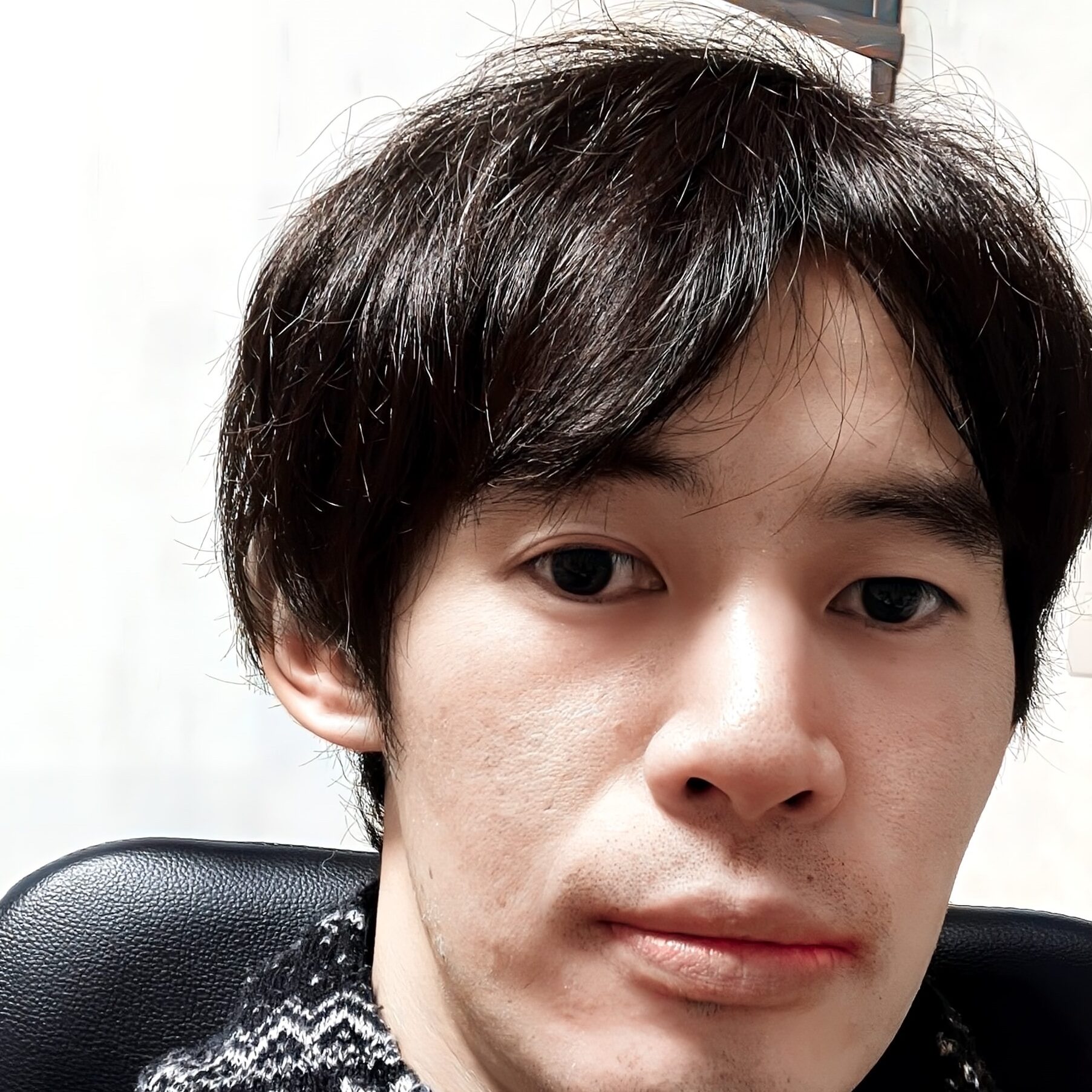
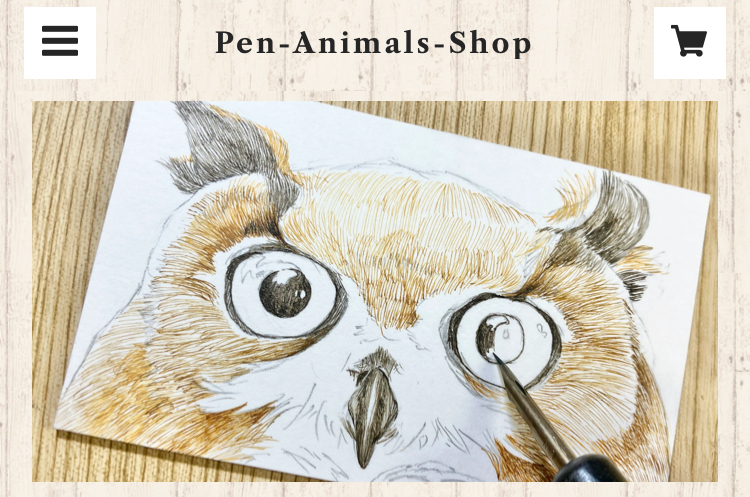
✅ 電子書籍『ペン画技法解説書』
✅ メール講座『絵の描き方』
✅ デッサン道具の知識
✅ アートで生きていく為の入門書
✅ メルマガ読者特別プレゼント
など、以下より受け取る事が出来ます。
⇩ ⇩ ⇩