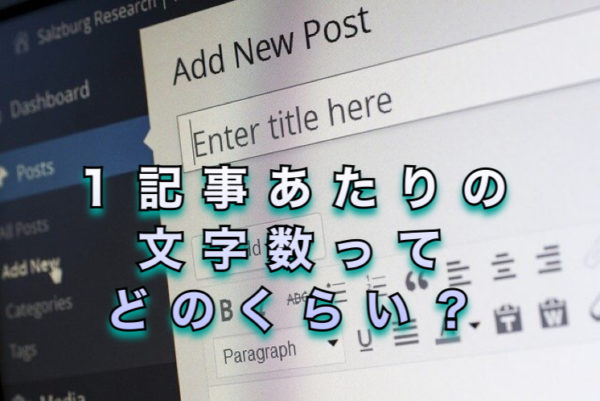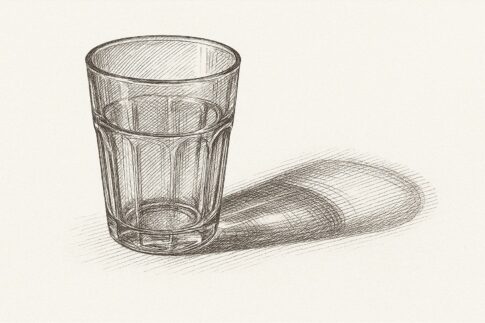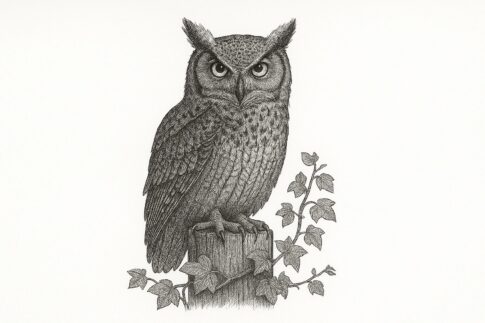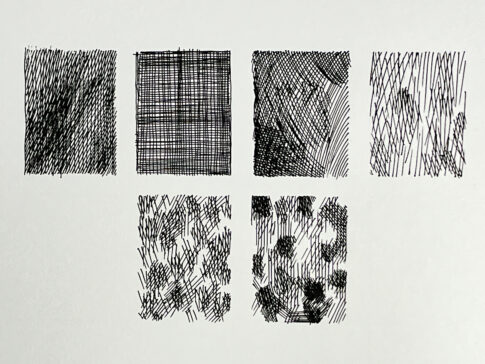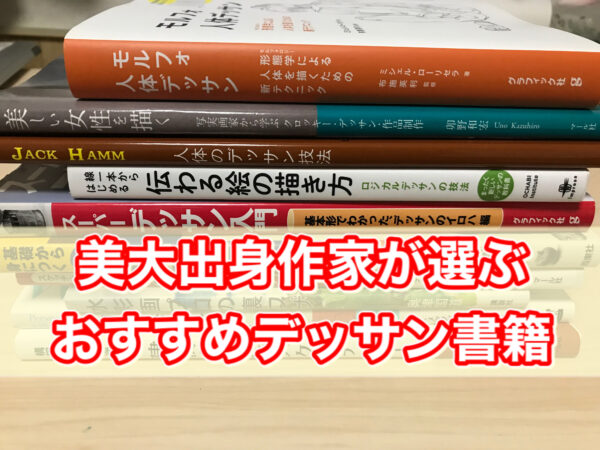ブログを続けていると、
ある日ふと手が止まる瞬間があります。
「書くことが思いつかない」
「どんなネタなら読まれるのか分からない」
そんなネタ切れ状態は、
多くのブロガーや
ホームページを運営する上で
誰もが通る道です。
ですが、実はブログのネタというのは
「思いつくもの」ではなく、
「見つけていくもの」です。
ネタ探しのコツを掴めば、
日常の中からでも無限に
アイデアを生み出せるようになります。
そこでこの記事では、
ブログネタを継続的に
生み出すための方法
というテーマについて
具体例と実践ステップ付きで紹介します。
今日から「もう書くことがない」と
悩む時間をゼロにしていきましょう!
ブログネタの探し方7選【実践で使える】
キーワードツールで「検索されるネタ」を見つける
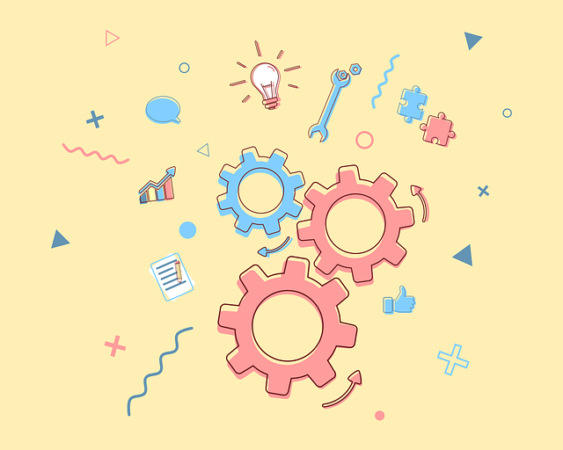
キーワードツールを使う事で、
自分では考えもしなかった
キーワードやネタを発掘する事が
出来るようになります。
そこで数あるツールの中でも、
まずは以下の3つを押さえておく事で
ネタ探しに困る事はなくなります。
・キーワードプランナー
・ラッコキーワード(旧good keyword)
・Googleトレンド
僕自身、主にこの3つの
キーワードツールを使って
ブログのネタを探しています。
これらのツールは基本的には無料ですが、
有料プランに加入する事によって
より便利な機能を使う事も出来ます。
お宝キーワードを探す上で、
より効果的に探したいのであれば
利用してみてくださいね。
Googleキーワードプランナー
Googleキーワードプランナーは、
Googleが無料で提供している
キーワードツールです。
⇨Googleキーワードプランナー
(クリックすると外部サイトにアクセスします)
利用する為には
Googleアカウントが必要となりますが、
このツールを利用する事で、
そのキーワードのおおよその
月間アクセス数や競合性などが分かります。
キーワードプランナーは
無料で使う事が出来ますが、
検索ボリュームがアバウトに
表示されてしまうといった
デメリットもあります。
(とはいえ無料でもこの機能は
かなりありがたいのですが)
また、広告費を払う事で
様々な機能を使う事が
出来るようになるので、
長い目で見たら
広告費を支払っておいた方が
良いかもしれません。
ラッコキーワード(旧good keyword)
キーワードを発掘する方法として
次に挙げられるのが
こちらのラッコキーワードです。
⇨ラッコキーワード
(クリックすると外部サイトにアクセスします)
先ほどのGoogleの
キーワードプランナーでは
検索ボリュームを
調べる事が出来ましたが、
コチラは関連キーワードが
順番に並んでいるので見やすいです。
また、有料プランに加入する事で、
キーワードプランナー同様に
検索ボリュームを調べる事が出来ます。
気になる方は加入してみてください。
ラッコキーワードの場合、
キーワードの関連語句を
大量に見つける事が出来ますし、
GoogleだけでなくYouTube、
Amazon、楽天、Bing等の
検索エンジンの選択も
可能となっています。
サジェストキーワード取得ツール
をうまく使う事で、
多い時には一つのキーワードで
1000件前後のキーワードを
見つける事が出来ます。
こちらも基本は無料で使えるので、
是非ともブックマークに
追加しておいてください。
Googleトレンド
こちらも上の2つ程ではありませんが、
よく使うキーワードツールです。
Googleトレンドはその季節に
検索されやすいトレンドキーワードを
見つける際に使っていますが、
こちらもキーワードを探す上で
重宝しています。
⇨Googleトレンド
(クリックすると外部サイトにアクセスします)
ある程度の検索数のボリュームが無いと
グラフとして表示がされませんが、
あらかじめ需要がある月を
調べる事が出来ますので、
季節需要のあるキーワードを探す際は
とても便利です。
例えば、
「サッカー ワールドカップ」
のように、
その時に検索されているキーワードを
知る事も可能です。
トレンド記事を書いて
ブログに仕込んでおく事で、
その時期が訪れると
一時的にアクセスが
増やす事が出来ます。
特に季節や年間行事や
イベントに関する記事は
3ヶ月くらい前から仕込んでおく事で、
毎年その時期になるとアクセスを
増やす事となります。
あなた自身のブログや
ホームページに合った
キーワードを見つける事で、
統一感を持たせつつも
バズらせてアクセスアップに
繋げていきましょう!
SNS(X/Instagram)で「話題のテーマ」を拾う

SNSはリアルタイムで
トレンドが生まれる場所です。
特にX(旧Twitter)で
- ブログネタ
- 発信
- コンテンツ
などで検索すると、
他の発信者がどんな内容で
注目を集めているかが見えてきます。
トレンドワードや
他のブロガーの方の発信から、
「今どんな話題が求められているか」
を把握することで、
時流に合ったネタが作れます。
【実例】
Xで“リライト方法”が伸びていたから、
それを自分流にまとめたら
CTRが2倍になった
SNSの反応は
その瞬間の世間における
“リアルな需要の指標”でもあります。
単なる参考ではなく、
読者の反応データとして
活用してみてください。
ニュースサイトやGoogleトレンドから追う

Yahoo!ニュースや
テレビニュースから
今話題になっているネタを
見つける事が出来ます。
特に自分が扱っているテーマに
関する話題であったり、
自分が興味のある分野に関する
内容であれば記事にする事も
出来るでしょう。
先ほどのSNSでネタを探す場合は
人々の関心を知る事が出来ましたが、
ニュースサイトと照合する事で
記事の説得力を増す事となります。
流行り廃りの内容であれば
瞬間的なアクセスとなってしまいますが、
瞬発力があるといった特徴がありますね。
特にGoogleトレンドは、
特定のキーワードの検索人気を
時系列で可視化してくれるツールです。
「ブログネタ」
「アクセス」
「SEO」
など自分のジャンルを入れると、
検索数が増えているテーマを
発見する事ができます。
特に季節・イベント
・新サービス系のネタは
一時的にアクセスが急増しやすい
傾向があります。
コツ:上昇ワードを拾って
「ブログ×話題」で記事化
例:「春におすすめのブログネタ」
「年末年始にアクセスが伸びる記事テーマ」
季節トレンドネタであれば、
毎年同じ時期になると
その度に需要があるので、
アクセスの底上げとなります。
これを見越した上で
季節トレンド記事の量産を
していく事も
一つの戦略としてアリですね。
ライバルサイトを調べる
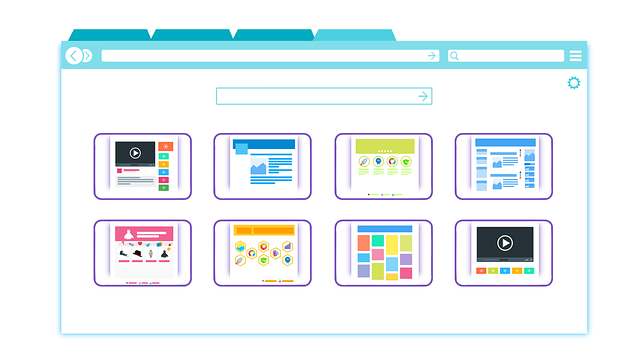
自分と同じテーマのブログや
サイトをチェックする事で
ライバルサイトを
研究する事が出来ますし、
アイデアやネタを
拾い集める事も出来ます。
もちろん、参考にする程度で
あれば構いませんが、
所々に通っていたり、
丸々コピペをするのは
著作権的にもダメですね。
仮に侵害をしてしまったら
以下の罰則が課せられてしまうので
気をつけましょう。
個人の場合:10年以下の懲役
または1,000万円以下の罰金、
またはその両方(著作権法第119条)。
法人の場合:3億円以下の罰金
(著作権法第124条)。
親告罪:基本的に著作権者の
告訴がなければ起訴されませんが、
営利目的の複製や配信などは
非親告罪となる場合もあります。
知らず知らずのうちに
侵害していないように
十分に気をつけておきましょう。
また、拾い集めたネタを
自分なりの解釈や言葉を付け加える事で
オリジナルの記事を書く事が出来ます。
特に検索上位表示されているブログは
参考になる記事の書き方をしているので、
研究してみると様々な
発見がある事でしょう。
自分の経験を元に記事にする

自身の過去を振り返ると、
様々な経験をしてきたと思います。
学生時代は進学や
進級に伴う環境の変化であったり、
社会人になったら
仕事や取引先の方との交流など、
多くの経験をしてきた事でしょう。
その際に、自分が悩んでいた事や、
どのようにしてその悩みに対して向き合い、
解決していったかという事は
記事のネタとしても
十分に扱えるものとなります。
自分の経験を元に書く方が
リアルに想像がしやすいですし、
その分、文章の説得力も上がります。
その結果自ずとクオリティが上がるので、
「記事ネタが思い付かなくて悩んでいる」
という方は過去の自分の経験を元に
書く事をオススメします。
ブログネタは外部からだけでなく、
自分の中にも眠っています。
過去に書いた記事の中で
アクセスが多いものを掘り下げたり、
自分の体験談をシリーズ化したりするのも
立派な新ネタです。
例:ブログのアクセスが伸びなかった
時にやった3つのこと
→ このような実録系は信頼を得やすく、
E-A-T強化にもつながります。
経験談は唯一無二の
オリジナルコンテンツです。
「自分にしか書けない視点」で書くと、
検索上位を狙いやすくなります。
読者の悩み・質問から逆算する

Yahoo!知恵袋やQuoraといった
質問サイトからネタを拾う事が出来ます。
日々、沢山の人が悩みを解決するべく、
サイトに投稿して解決の
方法を探っています。
質問サイトで質問されている
投稿に対する答えを記事にまとめる事で、
他にも同じような悩みを抱えている方への
アドバイスにもなり得てくるものです。
他の方の回答やベストアンサーも
閲覧する事が出来るので、
それらも参考にしつつ
記事にしてみると良いかもしれませんね。
特に
「どんな内容を書けば読まれるのか分からない」
という悩みの答えは、
読者の声の中にあります。
コメント欄、SNSリプ、検索サジェスト、
「Yahoo!知恵袋」などのQ&Aサイトも
宝の山です。
実践例
「ブログ 毎日更新 意味ある?」
→ 実際の検索がある
→ “毎日更新すべきか迷っている人”
向けの記事が成立。
読者が求めている答えを
そのままタイトル化すれば、
自然とSEOにも強くなります。
ブログやSNSでのコメント

コメント欄への質問やコメントの中には、
そのまま記事に繋がりそうな
ネタが見つかる事があります。
読者の興味関心に合わせた
記事のアイデアを得る事で、
記事を書く事が出来るようになります。
またSNSも同様で、
投稿に対するコメントがあった際に
それをネタにブログ記事として
書く事も可能です。
ブログネタを継続的に見つける3つの習慣
ブログを長く続けていくうえで、
多くの人がぶつかる壁が
「ネタ切れ」
です。
最初のうちは勢いで書けても、
ある時ふと手が止まってしまう..
それは誰にでも起こる自然なことです。
けれども、ネタを“思いつくもの”から
“仕組みで生み出すもの”へと
変えていければ、
この悩みは確実に減らせます。
ここでは、ブログネタを
継続的に見つけるための
3つの習慣についてお話しします。
ネタメモを常に残す習慣
まず1つ目は、
ネタメモを常に残す習慣
です。
ブログのアイデアは、
机の前よりも日常のふとした瞬間に
生まれることが多いものです。
たとえば通勤中、SNSを見ている時、
何気ない会話の中など、
インスピレーションのきっかけは
どこにでもあります。
だからこそ、思いついたことを
すぐに記録できる環境を整えることが
重要です。
スマホのメモアプリやLINEメモ、
あるいはNotionのようなツールを使えば、
思いつきを一言で残すだけでも
後々の財産になります。
大切なのは、「キーワード」ではなく
「気づき」を書き留める事です。
「こんな話題に共感した」
「この体験が印象に残った」
そんな感覚的なメモが、
後で読み返すと新しい記事の
きっかけになることがあります。
僕の場合、創作活動を行う過程で
制作の過程で得た感情や気づきなども
記事のネタにしています。
それらをストックしておくことで、
創作とブログの両方を
豊かにしていけるようになります。
SNSやニュースを観察モードで見る習慣
2つ目は、
SNSやニュースを
観察モードで見る習慣
です。
多くの人はSNSを情報の消費の場として
使っている人が大半ですが、
実は記事を描く上での
観察の場でもあったりします。
たとえばX(旧Twitter)で
「ブログネタ」
「発信」
「リライト」
などのキーワードを検索すれば、
どんな話題が今注目されているのかが
一目でわかります。
他にも、どんな言葉が共感を呼び、
どんな切り口の記事が
拡散されているかを観察することで、
自分の次の記事のヒントが得られます。
たとえば最近「継続できない理由」
というテーマが多くの反応を
得ていると気づいたら、
ブログを継続できない人の
特徴と対策
といった記事に応用できます。
このようにSNSをただ流し見るのではなく、
「なぜこの投稿が伸びたのか」
「どんな構成が読まれているのか」
という視点で見ると、
ネタの構造が見えてきます。
これはまさに“現代の
リアルタイム市場調査”ですね!
毎日10分だけでもいいので、
意識的に観察する習慣をつけると、
インスピレーションが
自然と湧いてくるので、
実践してみてください。
週に1時間のネタ仕込み時間をつくる習慣
そして3つ目は、
週に1時間のネタ仕込み時間を
つくる習慣
です。
多くの成功しているブロガーは、
ネタを探す時間を“予定”として
組み込んでいます。
思いついた時に考えるのではなく、
「週末の午前中」
「夜の静かな時間」
など、ネタを整理するための
時間を決めておくのです。
その1時間で、
新しいネタを10個ほど書き出し、
- すぐ書く記事
- 保留する記事
- ボツの記事
などに分類しておきましょう。
この作業を繰り返すだけで、
半年後には100件以上のネタストックが
自然に溜まります。
また、保留したネタの中には、
季節が変わった頃に
再利用できるものもあります。
僕の場合、特にテーマ性を持った
記事を書いている場合は、
“デッサン・ペン画の技法”
“心理系”
“アート系”
“画家として食べていく戦略”
などのカテゴリごとに
ネタを分類しておくと、
記事構成の軸も整いやすくなります。
この3つの習慣を意識するだけで、
ブログネタが自然と生まれる
サイクルが出来上がります。
ネタ切れは「才能の枯渇」ではなく、
「仕組みの欠如」から起こるものです。
思いつきを逃さず記録し、
情報を観察し、定期的に整理する。
この流れが身につけば、
もうネタに困ることはありません。
ブログは単なる情報発信ではなく、
日常の中の気づきを形にする
表現活動となります。
日々の習慣を整えることで、
ブログに書く記事のネタは
尽きることなく
湧き続けていくものとなります。
ブログネタの継続的な発想方法に関するよくある質問(FAQ)
Q1:ブログネタを継続的に
見つけるにはどうすればいい?
A1:日常での気づきをすぐに
メモする習慣を持つことが大切です。
思いつきを逃さない
仕組みをつくることで、
自然とネタが溜まっていきます。
Q2:SNSをどう活用すれば
ブログネタが見つかりますか?
A2:X(旧Twitter)や
Instagramを観察する視点で
見ることです。
話題になっているテーマや
共感を呼ぶ投稿の構造を分析すれば、
今求められているネタを把握できます。
Q3:ネタを考える時間がない場合は
どうすればいいの?
A3:週に1時間だけ
「ネタ仕込み時間」を
設けてください。
短時間でも継続すれば、
数ヶ月で数十件のストックが
自然に溜まります。
Q4:同じような内容を書いても大丈夫?
A4:大丈夫です。
同じテーマでも
「視点」や「体験談」
が違えば立派な
オリジナル記事になります。
焦らず自分の言葉で
再構成していきましょう。
Q5:日常生活からネタを
見つけるコツはありますか?
A5:通勤・買い物・会話など、
何気ない出来事の中にある気づきを
大切にしましょう。
感情が動いた瞬間こそ、
読者の共感を呼ぶ記事の原石です。
まとめ
ブログのネタを探す
方法についてまとめました。
自分の頭で捻り出そうとすると
どこかで限界が訪れてしまうかも
しれません。
世の中の話題や関心を集めている
テーマなどを知ったり、
需要があるキーワードを見つける事で
文章の幅も広がります。
今回紹介した方法で、
あなたなりのネタ探しを
見つけてみてくださいね!