「なんとなく色を選んでしまって失敗した…」
そんな経験はありませんか?
絵を描く上での色選びからデザインまで、
色の扱い方には幅がありますが、
「正直言って色選びはセンスなんじゃ..」
そんな風に落ち込んでしまった人も
いるかもしれません。
ですが、理論的に色彩について学ぶ事で
センスに頼るのではなく、
誰しも色彩感覚を養う事が
出来るようになるのです。
実は色にはルールがあり、
その一つとして
「補色(ほしょく)」
という考え方があります。
たとえば赤と緑、青とオレンジなど、
対照的な色同士をうまく使うことで、
デザインやコーディネートも
センスよく仕立て上げる事が
出来たりもします。
そこでこの記事では、色の基礎である
「補色」
について初心者でもわかるように解説し、
すぐに使えるテクニックまで
ご紹介をしていきます!
補色とは何か?基本の意味と色の仕組みをわかりやすく解説

補色の定義とは?
補色(ほしょく)とは、
色相環(しきそうかん)
という色の輪の中で、
ある色の正反対に
位置する色のことを指します。
たとえば、
「赤」の補色は「緑」
「青」の補色は「オレンジ」
「黄」の補色は「紫」
といった具合です。
この関係は視覚的にもっとも強い
コントラスト(対比)を生むため、
デザインやアート、ファッション等の
分野において、とても重要な
考え方となります。
補色は英語では
「complementary color」
と呼ばれ、「補う色」という
意味があります。
例えば、
補色にはある色が足りない要素を
補ってくれる
というイメージです。
視覚的なバランスや
インパクトを出すために
補色は非常に効果的です。
ある部分を目立たせたい、あるいは
強調したい部分に補色を使う事で、
人の目に自然と引きつける
力を持っています。
実際にデザインや絵画に取り入れる際に
使い所は難しいかもしれませんが、
補色は色の基礎知識の中でも
特に重要な概念のひとつですので、
是非とも覚えておきたいものです。
補色を理解することで、
色使いの配色や理論、センスが
一気に上達していくので、
是非とも補色について
マスターしておきましょう。
色相環と補色の関係
色相環とは、色を順番に円形に
並べた図のことで、
赤→橙→黄→緑→青→紫
というように、虹のような順番で
構成されています。
補色というのは、つまりこの色相環上で
真逆の位置にある色同士の事を指します。
たとえば、下記のような色相環では
| 色 | 補色 |
|---|---|
| 赤 | 緑 |
| 青 | オレンジ |
| 黄 | 紫 |
| 青緑 | 赤橙 |
| 黄緑 | 赤紫 |
このように色を対応させて
補色を見つけることができます。
色相環を理解する事で、
色と色の関係性が視覚的に
わかりやすくなるため、
補色だけでなく類似色や
トライアド(3色配色)などの応用も
効くようになります。
デザインにおいては、
色相環を使って色を選ぶことが
基本のスキルになりますので、
まずはこの表をしっかり
頭に入れておくと良いでしょう。
実生活で見られる補色の例
補色の関係は実際の生活の中でも
よく目にします。
例えば以下のような色の組み合わせが
よく知られています。
- 赤 × 緑:クリスマスカラーの定番。強いコントラストでお互いを引き立て合います。
- 青 × オレンジ:スポーツチームやイベントバナーなどでよく使われる組み合わせ。
- 黄 × 紫:和のデザインやファッション、和菓子などでも見られる華やかな配色です。
このように、補色には
「派手」「目立つ」
といった印象を与えることが多く、
人の目を引くために最適な
配色とされています。
ただし、配色のバランスを考えずに使うと
派手すぎて逆効果になる場合もあるので
注意が必要です。
いくら目立つからと言って
何でもかんでも補色ありきの
デザインになってしまうと、
かえって落ち着かない配色に
なり兼ねませんからね。
補色と対比効果の関係
補色同士を並べると、
色の対比効果が非常に強くなります。
つまりこれは
「視覚の錯覚」
「コントラスト効果」
とも呼ばれます。
例えば、赤と緑を並べると
それぞれの色がより鮮やかに
見えるといった形です。
この現象は
「同時対比」
とも関係しており、
人間の目は周囲の色の影響を受けて
色の見え方が変わる特徴があります。
これを利用することで
特定の部分を強調したり、
印象に残るデザインを
作ることができます。
「補色残像現象」ってなに?
「補色残像現象」
とは、ある色を一定時間見たあとに
白い壁を見た際に
その補色が見えるという
視覚現象の事です。
たとえば、赤い丸をじっと見つめてから
白い紙を見ると、緑色の丸が
見えることがあります。
これは、目の中にある視細胞が
特定の色に反応しすぎて、
一時的にその色に対する感度が下がり、
逆の色(補色)が見えるように
なる為となります。
この現象も、補色が人の視覚に
深く関係していることを
示す面白い例です。
このような残像現象を理解する事で、
色の心理的・生理的な影響まで
把握できるようになります。
デザインやアートの表現にも
活かせる知識ですね。
補色が使われる代表的な場面とは?

デザインと補色の関係性
補色の関係性は、グラフィックデザインや
Webデザインで非常に重宝されます。
色同士が強く引き立て合うため、
視線を集めたいパーツに対して
補色を使うと効果的です。
特にCTA(Call To Action)ボタンなど
「クリックしてほしい」箇所では、
背景とのコントラストを
考えた補色を使うことで、
ユーザーの視線を自然と誘導できます。
企業のロゴやアプリのアイコンでも、
補色の使い方ひとつで
ブランドイメージが大きく
変わることもあります。
Adobeなどのプロ向けデザインソフトにも
補色を自動で選んでくれる機能があり、
初心者でも安心して使えるのが魅力です。
補色はなぜ広告でよく使われるのか?
広告の世界では
「一瞬で目を引く」
事こそが命です。
そのため、視覚的にインパクトの強い
補色の組み合わせが
多く使われています。
補色を使うことで、
自然と目が向くようになるのは
人間の視覚の仕組みに基づいた
テクニックです。
強いコントラストを持つ補色は
見る人の注意を引きつけ、
記憶にも残りやすくなるのですね。
さらに、感情にも影響を与える
力があります。
たとえば、赤と緑は情熱と安心感を
それぞれ刺激します。
これらを組み合わせることで、
「買いたい!」「見たい!」
という気持ちを引き出せるわけです。
広告の世界では、補色の活用が
売上や反応率にも直結するため、
プロのデザイナーは意識的に
補色の組み合わせを
使いこなしています。
補色の使い方で失敗しないコツ

色の主張が強すぎる場合の対処法
補色はインパクトが強いため、
使い過ぎてしまうとどうしても
「ギラギラ」
「うるさい」
といった印象になってしまいます。
これはデザインでもファッションでも
言える事でもあります。
そんな時に重要なのは、
「彩度」と「明度」
これらを調整して
お互い引き立て合う色味に
することです。
たとえば、赤と緑を使いたい場合でも、
片方の色の彩度を落とした
「くすみカラー」にするだけで、
グッとおしゃれで落ち着いた
雰囲気に変わります。
もうひとつのポイントは、
色の使用面積を調整する事です。
目立たせたい色を「少量」に、
ベースカラーは「広く」使うことで、
バランスがとりやすくなります。
補色は、主張の強さを逆手に取れば
とても便利な存在です。
「抑える」テクニックを知っていれば、
どんな場面でも失敗しにくくなるので
必要な場面で活用してみてください。
中間色・無彩色との組み合わせで調整する方法
補色同士の色が強すぎると感じたら、
「中間色」or
「無彩色(白・黒・グレー)」
を間に挟むと見た目が落ち着きます。
たとえば、赤と緑の間に
グレーの背景を挟むことで、
色の強さが和らぎ、
文字が読みやすくなります。
中間色は彩度や明度が中くらいの色で
視覚的な刺激が少ないため、
強い補色の緩衝材としてぴったりです。
代表的な中間色は
ベージュやカーキ、ライトブルー
などがあります。
また、無彩色はどんな色とも
調和しやすいため、
デザイン全体を引き締める
役割もあります。
補色をそのままぶつけるのではなく、
間にワンクッションを入れることで、
「調和」と「目立ち」
の両方をうまく両立し、
バランスよくまとめる事が
出来るようになるのです。
トーンを揃えると補色もなじみやすい
補色同士は本来
強いコントラストを生むため、
派手に見えることが多いです。
しかし同じ「トーン(色調)」を
揃える事で不思議と統一感が生まれ、
なじみやすい印象になります。
たとえば、ビビッドな赤と緑は
クリスマスのように華やかですが、
両方をパステルトーンにすると
柔らかく優しい雰囲気に変わります。
また、くすんだトーン
(グレイッシュトーン)で合わせる事で
落ち着いた大人っぽい印象になります。
色のトーンを合わせると、
補色の相反している感じが和らぎ、
むしろおしゃれに見えるのが
ポイントです。
特にインテリアやWebデザイン、
ファッションなどでは、
トーンコントロールが仕上がりの
印象を大きく左右します。
補色を使いこなすには色そのものだけでなく
「トーン」という視点を持つことも
とても重要です。
これにより、デザインの幅が一気に広がります。
配色比率「7:2:1」の法則とは?
デザインでよく使われる黄金比率が
「7:2:1」という配色バランスです。
これは、
- ベースカラー7割
- メインカラー2割
- アクセントカラー1割
の割合で色を配置するという法則で、
補色を使う際にも非常に効果的です。
たとえば、
- 背景にベージュ(ベース)
- 主要な文字や要素にネイビー(メイン)
- 強調したい部分に
- オレンジ(ネイビーの補色)
これらを使う事で
全体のバランスが整って見やすくなり、
かつ目立つ部分がはっきりします。
補色はコントラストが強いので、
全体の中で「1割程度」に留めるのが
失敗しにくい使い方です。
配色比率のバランスを考える事で、
色の主張が適度になり、
見た目の心地よさにも繋がります。
この「7:2:1」は初心者でも
使いやすい法則なので、
ぜひ実践してみてくださいね。
補色を学んで色のセンスを磨こう!

色の基礎知識がセンスの土台
「センスがいい」と言われる人の多くは
感覚だけでなく、基本的な知識を
しっかりと持っています。
色のセンスも同様で、補色や類似色、
色相環といった基礎を知っている事が
デザイン力やコーディネート力の
土台になります。
色は感覚だけで選んでしまうと
失敗しやすくなります。
派手すぎたり、まとまりがなかったり…。
でも、補色を「狙って使う」ことができれば、
見る人に「洗練された」「プロっぽい」
という印象を与えることができます。
また、基礎知識を持っていれば、
流行や好みにも柔軟に対応でき、
自分らしいスタイルを
築きやすくなります。
センスは生まれつきではなく、
学ぶことで誰でも身につけられるものです。
色彩センスを育てる毎日の習慣とは?
色彩センスを磨くには、
毎日少しずつ色を意識する習慣が
大切です。
たとえば、街の看板や広告を見て
「この色は補色だな」と考えたり、
服を選ぶときに色の組み合わせを
意識してみたりすると、
自然と感覚が育っていきます。
また、スマホで「今日見た好きな色」を
1色だけメモする習慣もおすすめです。
1週間分の色を集めてみると、
自分の好みの傾向や補色の使い方にも
気づけるはずです。
日常にある色を観察し、
「なぜこの色に惹かれたのか?」
と考えるクセをつけることで、
理論と感覚の両方が磨かれます。
色の世界はとても奥深く、
学べば学ぶほど楽しくなる分野です。
ぜひ日々の生活の中で
補色を意識してみてください。
まとめ
補色とは、色相環で正反対に位置する
色同士のことを指し、
強いコントラストと目立つ効果を持つ
非常に重要な色の組み合わせです。
赤と緑、青とオレンジなど、
日常のさまざまな場面で
見かけることができます。
この記事では、
補色の基本から使いどころから
失敗しないテクニック、
さらには便利なツールや学習リソース、
日常での活用方法までを
詳しく紹介しました。
理論だけでなく、実践や観察によって
補色の使い方はどんどん身につきます。
補色を使いこなせるようになると、
デザインやアートのセンスが
磨かれるだけでなく、
モノの見方にも変化を
与えてくる事となります。
ぜひ日常生活の中で、
補色の魅力を発見してみてください。

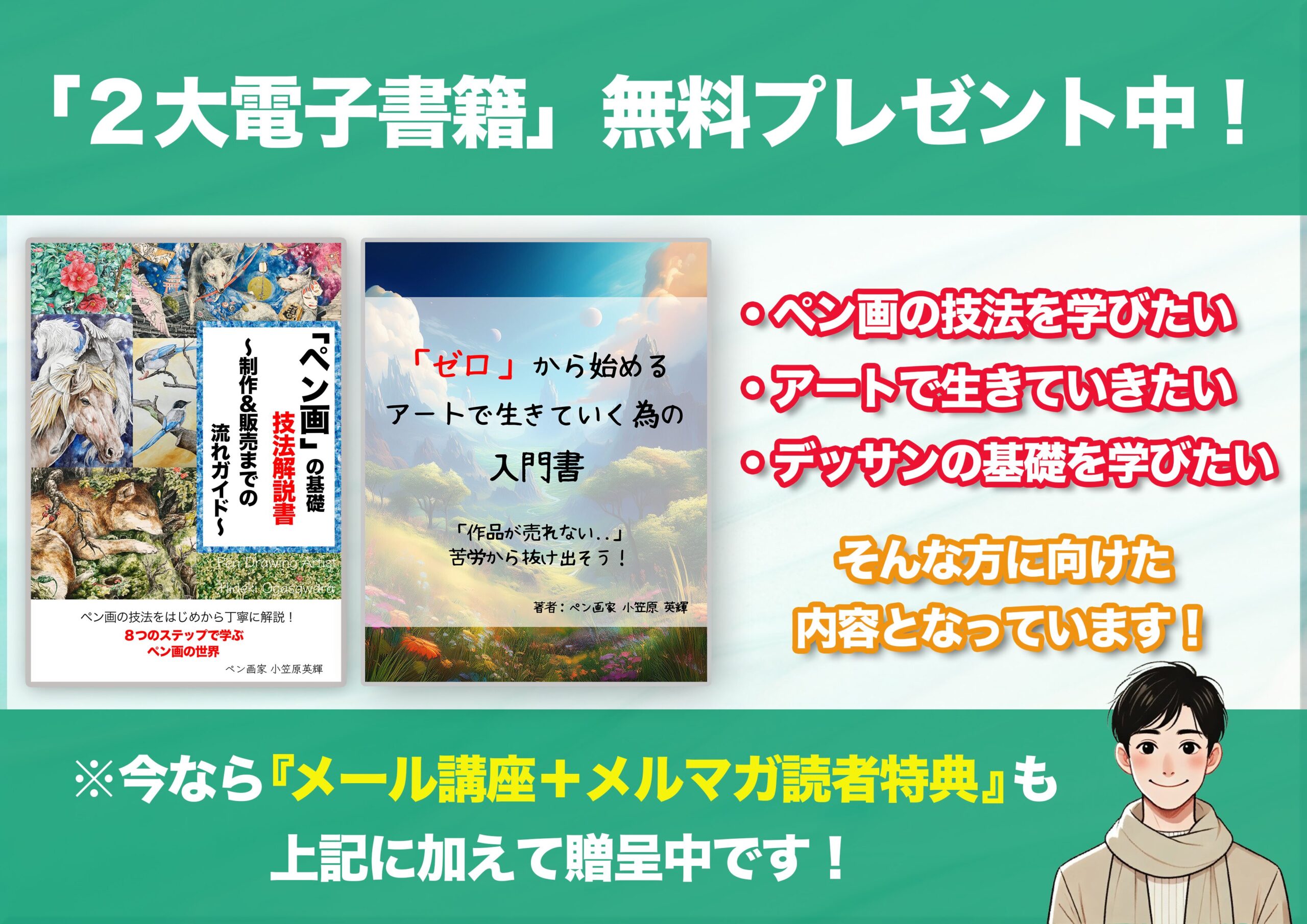

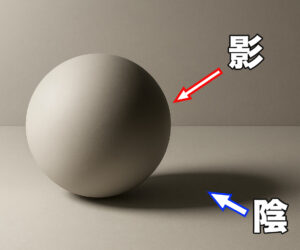



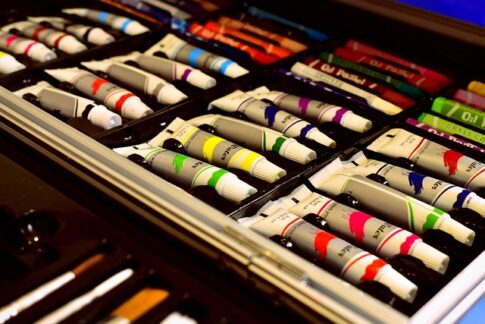

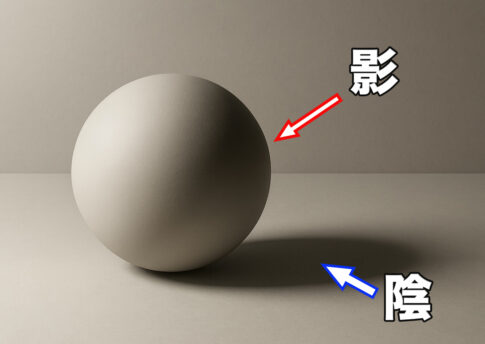
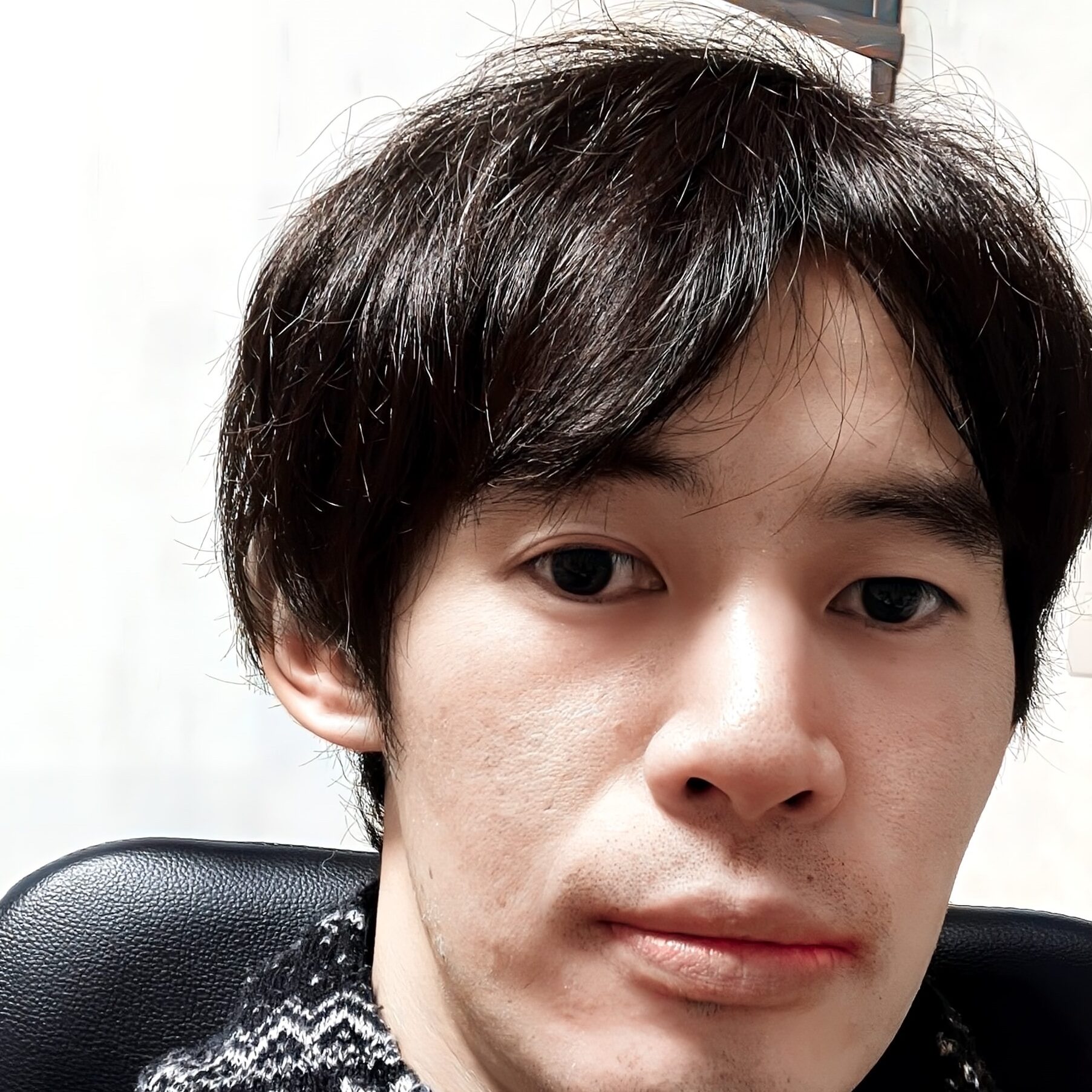
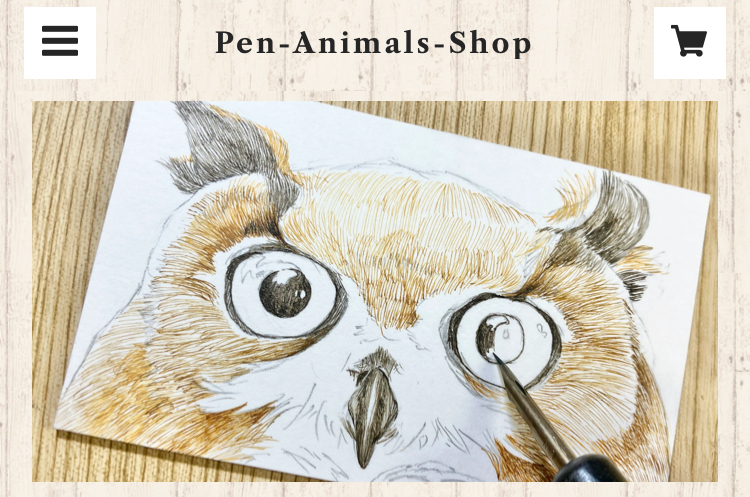
✅ 電子書籍『ペン画技法解説書』
✅ メール講座『絵の描き方』
✅ デッサン道具の知識
✅ アートで生きていく為の入門書
✅ メルマガ読者特別プレゼント
など、以下より受け取る事が出来ます。
⇩ ⇩ ⇩